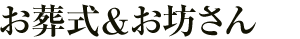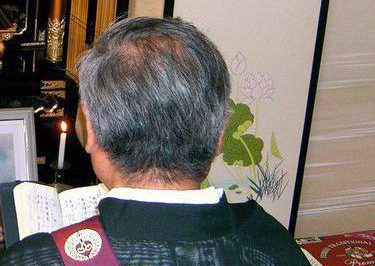良心的なお坊さん

安い・良心的お布施



良心的なお坊さんの葬儀での読経、法事・法要での読経
お坊さん、どのお葬式でも対応



近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、
お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀にも対応します。
葬儀社とお坊さんの依頼方法
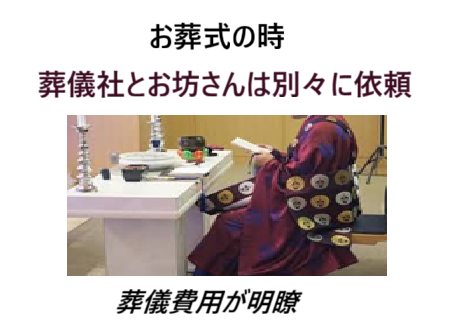
葬儀社とお坊さんは別々に依頼
お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼のこと
お葬式・家族葬は、お葬式後の法事・法要を考えて依頼しましょう
檀家としてのお付き合い不要 
「お葬式&お坊さん」は、檀家としてのお付き合いは不要です。その時々のお付き合いです。
「お葬式・法事」お坊さんに直接依頼
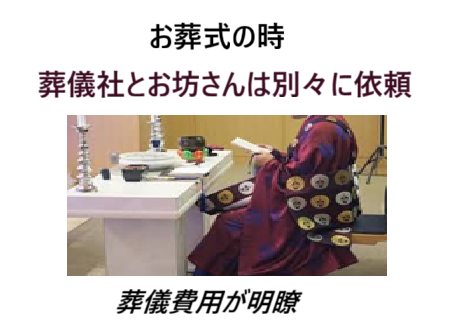 | 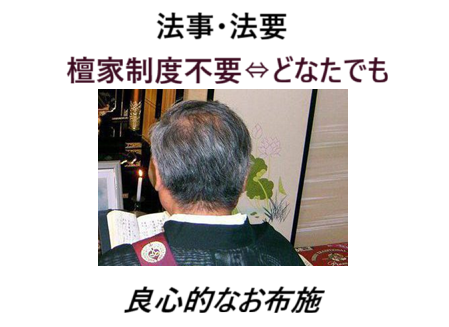 |
檀家制度は不要というお坊さんに直接依頼⇔「お葬式&お坊さん」
葬儀(お葬式)後の四十九日法要


葬儀(お葬式)が終われば、故人の供養を行わなければなりません。
葬儀後に七日毎に行うのが中陰法要(初七日法要~六七日法要)で、最後の七七日後が四十九日法要(満中陰法要)です。
四十九日法要(満中陰法要)

葬儀後の四十九日法要
四十九日法要とは、人の死後の49日目に行う法要のことです。
仏教では、死亡日を含め49日間を「中陰」と言って七日毎にお勤めをします。
死亡日から数えて七日目を「初七日」、次の七日目を「二七日」、次に「三七日」、「四七日」、「五七日」、「六七日」、最後の七七日の四十九日目が「満中陰」となります。
人が亡くなると、極楽浄土に行けるかの裁判が七日毎に行われると言われています。
極楽浄土に行けるように七日毎に法要を行うのです。
只、近年では七日毎に法要を行うのは難しいため、最初の裁判が行われる「初七日」と最終裁判の「四十九日」の法要を行うのが一般的となってきました
故人が迷わないための仏事ごと
葬儀後の49日法要は大切な仏事ごと
一般的には、故人が迷わずに極楽浄土に行ける(成仏する)ように七日毎の法要を行います。
存命中に悪行を重ねた人間でも、七日毎の供養を行うことで故人は迷わず極楽浄土に行けると考えられています。
私たち浄土真宗は、身内の死の悲しみの中から故人の遺徳を偲ぶとともに、これを縁として人生の拠り所となるお念仏の教えを聞き、阿弥陀如来さまへの報謝の念を深めるための仏事ごととしております。
葬儀(お葬式)後の中陰法要の一回一回が、大切な仏縁であるわけです。
檀家としてのお付き合い不要

檀家制度は、江戸時代に江戸幕府が私たちを管理するためにお寺に命じて作った制度です。
私たちはお寺に管理されるとともに身分の保証をされました。
その反面、お寺にお布施を施す義務が課せられました。
法要の参考⇒檀家制度
お盆(初盆)法要

お盆は、ご先祖を敬い、残された者の感謝の気持ちを込めて行われる日本の伝統的法要です。
この法要は、「盂蘭盆経(うらぼんきょう)に由来し、故人の魂を供養するという意味があります。
お盆は、迎え火や送り火、お墓参りなど様々な風習が各地で行われてきました。
お盆のことを「盂蘭盆会(うらぼんえ)ともいいます。
その他の法要

○ 1周忌法要 ○ 3回忌法要 ○ 7回忌法要 ○ 13回忌法要 ○ 17回忌法要
迷信に惑わせれないこと

四十九日法要に関して、「四十九日が三月にわたるといけない」という迷信が広くいきわたっているようです。
三月にわたる前に、法要を済まそうとします。
五七日(35日)に法要を行ったり、それ以前の日曜日など、休みの日に済ませたりします。
しかし、よく考えればわかることですが、月の15日以降の後半に亡くなると、当然、四十九日が三ヵ月にわたってしまいます。
月の後半に亡くなれば、三ヵ月にわたってしまうのに、「四十九日が、三ヵ月にわたるといけない」というのは「始終苦(しじゅうく)が身につく(三月)」からだということです。
これは、完全なる語呂合わせでしかない迷信なのです。
お葬式の時、お坊さんは
葬儀社とは、別に依頼
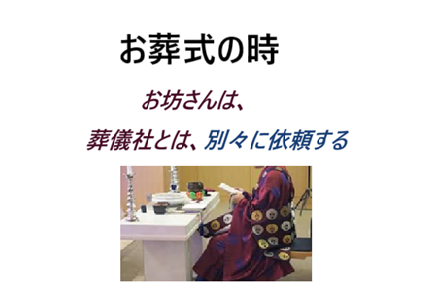
葬儀社とお坊さんは、
別々に依頼!
お葬式の時、お坊さんの読経(お経)は葬儀社とは、別々に依頼すること(大原則)葬儀費用が明瞭
近年の葬儀後の法要状況
近年、宗教離れ・仏教離れから法事・法要を執り行わない方も出てきております。
お葬式に於いても、仏式葬儀では無い葬儀で行う方や葬儀式自体を行わない直葬でのお葬式をされる方も出てきております。
ですが、人として生きていくうえに於いては、法事・法要は大切な仏事ごとだと思います。
葬儀・法事の読経対応地域